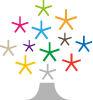学びのカモコレとは?
2024年2月13日
学びのカモコレ
 Top
Top
現在の蒲生小学校には昔、「永興寺」という大きなお寺がありました。
大定山護法院永興寺は室町時代前期、量外和尚によって開かれた蒲生氏の菩提寺です。
曹洞宗に属し、7つの伽藍と多くの末寺を持つ大きなお寺でしたが、廃仏毀釈により廃寺となりました。


目抜き通りの八幡馬場は、一般通行のほかに諸行事、祭礼など多目的に使われていました。
八幡馬場の幅は最も広い約8メートルで、両脇には水路がありました。
蒲生麓にある他の馬場は幅約6メートル、小路は幅約2メートルでした。


江戸時代は藩の支配が厳しく、在郷武家でも茅葺きの家が多くみられました。
武家屋敷では、門の内側に石垣を複雑に築き、奥に直接入れないような仕組み(武者返し)に造ることが多くあり、いざという時の防御のためと言われています。


保安4(1123)年、当時の蒲生院の惣領職となった蒲生上総介舜清が、豊前国(現在の大分県)の宇佐八幡宮を勧請し、蒲生の総社としました。
境内には樹齢約1500年の巨樹「蒲生の大クス」があり、昭和63年に環境庁(現環境省)により日本一大きい木と認定されました。