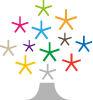新着記事
-
蒲生麓 標柱
五千人の産婆さん (日高フジ産婆宅跡)標柱5
後田集落に“名産婆”で知られた日高フジさん(旧姓丸野)は昭和8年から46年までの39年間で約五千人の赤ちゃんを取り上げました。
夜中のお産に備え、常にモンペをまとって床に入り、どこにでも出向いたため一ヶ月にゲタを2足ははきかえていました。
昭和63年、94歳で亡くなられた今なお多くの人々の心に残っています。2023年6月16日詳しく見る五千人の産婆さん (日高フジ産婆宅跡)標柱5
2023年6月16日蒲生麓 標柱 -
蒲生麓 標柱
永興寺(よくし)跡 標柱4
現在の蒲生小学校にはむかし、大きな永興寺というお寺がありました。大定山護法院永興寺は明徳年間(1390~1393)の室町時代に量外和尚によって開かれた蒲生の菩提寺でした。曹洞宗惣持寺派に属し、七つの伽藍と多くの末寺を持つ大きいお寺でしたが、明治2年に廃仏毀釈により廃寺となりました。
2023年6月16日詳しく見る永興寺(よくし)跡 標柱4
2023年6月16日蒲生麓 標柱 -
蒲生麓 標柱
八幡馬場 標柱2
道路は、一般通行のほかに諸行事、祭礼など多目的に使われ、「馬場」と呼ばれて目抜き通りの八幡馬場は幅8メートルと設定されていました。蒲生麓集落にある他の馬場は幅6メートル、小路は2メートルでした。
2023年6月16日詳しく見る八幡馬場 標柱2
2023年6月16日蒲生麓 標柱 -
蒲生麓 標柱
清水家 旧郷士屋敷 標柱3
江戸時代は藩の支配が厳しく、在郷武家でも茅ぶきの家が多くみられました。武家屋敷では、門の内側に石垣を複雑に築き、奥に直接入れないような仕組みに造ることが多く、いざという時の防御のためだと言われています。
清水家は現在の蒲生茶廊zenzaiとして活用されています。2023年6月15日詳しく見る清水家 旧郷士屋敷 標柱3
2023年6月15日蒲生麓 標柱 -
 蒲生麓 標柱
蒲生麓 標柱蒲生八幡神社 標柱1
保安4年(1123)、当時の蒲生院の惣領職となった蒲生上総介舜清が、豊前国(現在の大分県)の宇佐八幡宮を勧請し蒲生の総社としました。境内には樹齢約1,500年の巨木「蒲生の大クス」があり、昭和63年度に環境庁により日本一大きい木と認定されました。
2023年6月15日詳しく見る
蒲生八幡神社 標柱1
2023年6月15日蒲生麓 標柱 -
 日本遺産
日本遺産蒲生八幡神社
保安4年(1123)に蒲生氏初代・上総介舜清(かずさのすけしゅんせい)が、豊前国宇佐八幡宮を勧請して創建。島津義弘による社殿や鳥居の修築以降は、歴代薩摩藩主の厚い保護を受け、また蒲生の総社として広く崇敬されている。
2023年1月6日詳しく見る
蒲生八幡神社
2023年1月6日日本遺産 -
 日本遺産
日本遺産太鼓踊り
島津義弘公由来の伝統芸能。その勇壮さから凱旋踊りとして、または流行病を鎮める効果があるとして、県内各地で伝承されている。明治時代以降、蒲生では義弘公命日の旧暦7月21日(現在は8月21日)に一般公開し、蒲生八幡神社へ奉納している。
2023年1月6日詳しく見る
太鼓踊り
2023年1月6日日本遺産 -
 日本遺産
日本遺産蒲生の紙漉き
蒲生は古くから手漉き和紙の製造で知られ、島津家の家老職が武士に藩の御用紙を製造させたのが始まりとされている。豊かな水と原料に恵まれていた蒲生には、全盛期に約300人の手漉き紙職人がいたと言われている。
2023年1月6日詳しく見る
蒲生の紙漉き
2023年1月6日日本遺産 -
 日本遺産
日本遺産掛橋坂
藺牟田・ 祁答院と蒲生を結ぶ全長661mの地方街道。江戸時代には帖佐郷にあった薩摩藩の御蔵までの年貢米輸送などに利用されていたが、道幅が狭く危険な板敷で、道中最も厳しい難所だったとされる。大河ドラマ「西郷どん」のロケ地となった。
2023年1月6日詳しく見る
掛橋坂
2023年1月6日日本遺産 -
 日本遺産
日本遺産御仮屋犬槙(一ッ葉) 蒲生御仮屋門
御仮屋犬槙(一ッ葉)
蒲生地頭御仮屋の表庭に植えられていた樹で、樹齢約400年、樹高10m、根回り4m。幹内は空洞化しているが、樹勢は保たれている。犬槙のことを鹿児島ではその形状から「一ッ葉」と呼び、江戸時代は生垣として利用されていた。
蒲生御仮屋門
蒲生地頭御仮屋の正門で、文政9年(1826)に再建された。反り瓦屋根の両脇には小屋根が、前方には袖が出ていて、乳鋲を打った観音開きの大扉や不浄門などに当時の面影を見ることができる。2023年1月6日詳しく見る
御仮屋犬槙(一ッ葉) 蒲生御仮屋門
2023年1月6日日本遺産
SHARE
- ホーム
- 新着記事